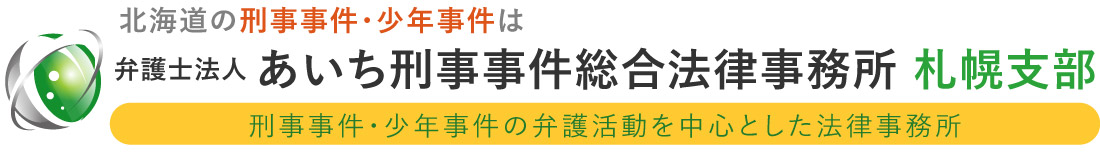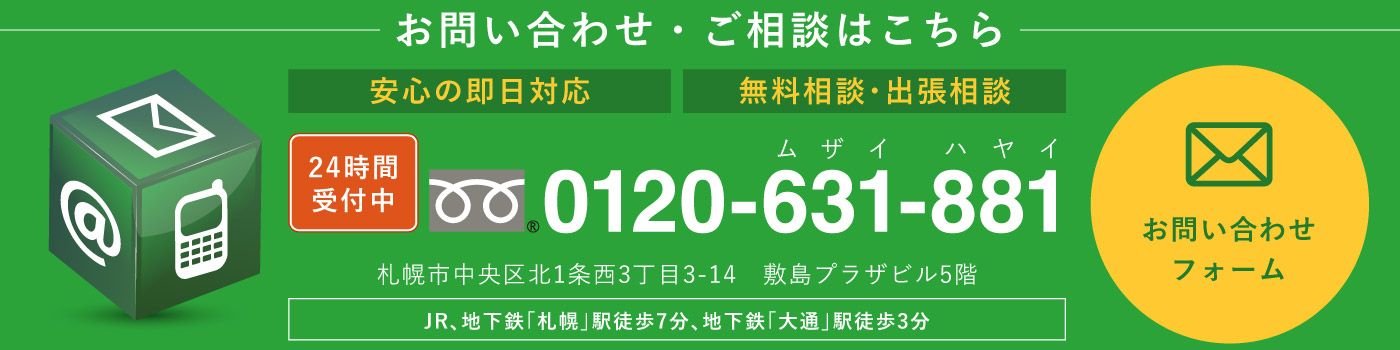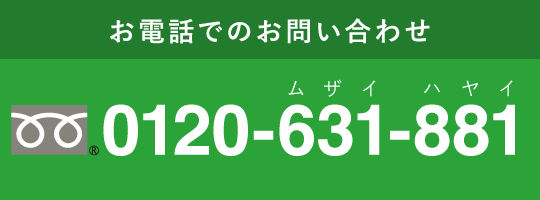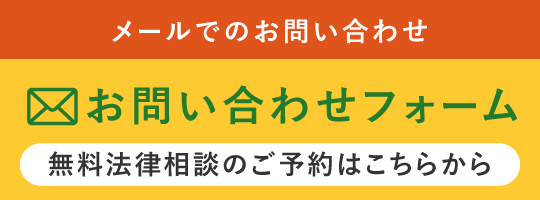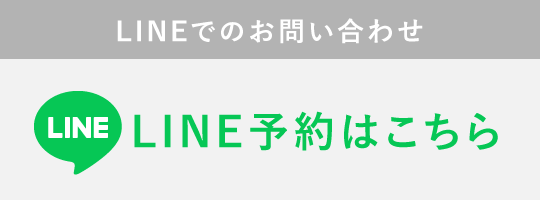※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
執行猶予には刑の全部の執行猶予に加えて刑の一部の執行猶予があります。
執行猶予
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができます(刑法25条1項)。
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予されたものが2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、その刑の全部の執行を猶予することができます(刑法25条2項本文)。
ただし、再度の執行猶予で保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、その刑の全部の執行を猶予することができません(刑法25条2項但書)。
もっとも、罰金刑で執行猶予がされることはほぼありません。
強盗罪など一部の刑は短期が3年を超えているため、酌量減刑(刑法66条)等が付かないと執行猶予を付けることができない場合があります。
保護観察
執行猶予の期間中保護観察に付することができます。執行猶予期間中に再度の執行猶予となったときは、必ず保護観察に付されます(刑法25条の2第1項)。
保護観察中は遵守事項を遵守し、保護司の指導に従い、生活改善をしていくことになります。
執行猶予の必要的取消し
- 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
- 猶予の言渡し前に他の罪ついて拘禁刑以上の刑に処されたことが発覚したとき
以上の場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
③については、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処されたことがない者(刑法25条1項2号)や他の罪についてその刑の全部の執行を猶予されたことが発覚した者(刑法26条の2第3号)であった場合はこの限りではありません。
執行猶予の裁量的取消し
- 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき
以上の場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができます。
執行猶予取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
上記の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
執行猶予の猶予期間経過
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います。
ただ、前科としては残ります。
刑の一部の執行猶予
従来は刑の全部の執行猶予か全て実刑を受けるかしかありませんでした。
しかし、再犯の防止のためには執行猶予で社会に出してそのままにするのも、刑務所で拘禁刑に付させるだけでも十分ではないことから、刑務所での拘禁刑に服している間社会復帰の準備をし、執行猶予で社会に戻りつつ復帰の準備を図るため、刑の一部の執行猶予をすることができるようになりました。
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
- 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
以上の者が3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
その一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算することになります(刑法27条の2第2項)。
一部執行猶予の期間中も保護観察に付することができます(刑法27条の3)。
一部執行猶予の必要的取消し
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき
以上の場合は、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されます。
ただし、③の場合でその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない場合は、必ず取り消されることにはなりません。
一部の執行猶予の裁量的取消
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき
以上の場合は、刑の一部の執行猶予の言渡しは取り消されることがあります。
一部執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
一部執行猶予期間経過の効果
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽されます。
この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとします。
執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。
1 再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
2 保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。
改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
3 執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。