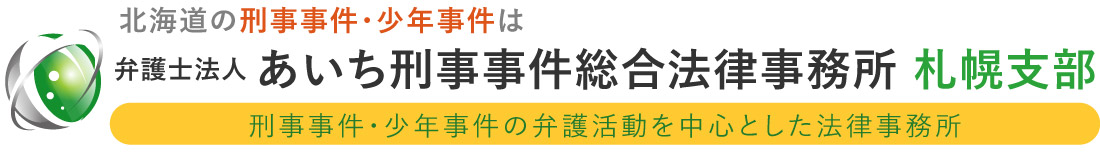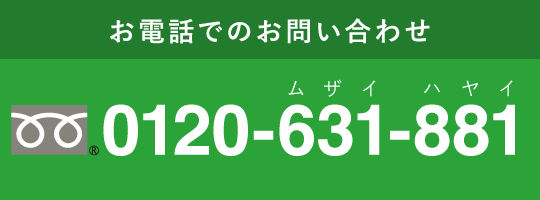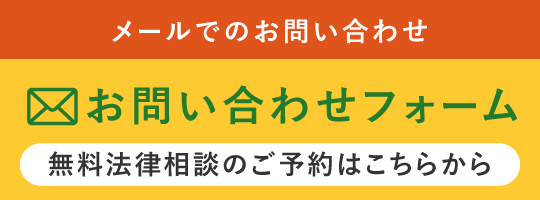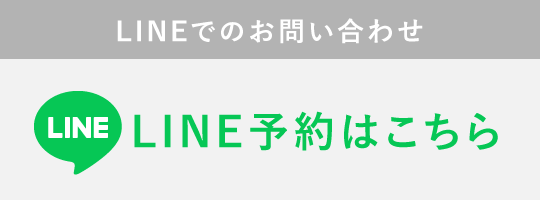罪を犯したとして逮捕・勾留されては、是非とも無実又は無罪を証明したいという強い思いに駆られるでしょう。しかし、無実・無罪の証明は極めて困難である上に、その必要もありません。
無実・無罪の証明
自分が無実であることを証明することは極めて困難です。それはやっていないことを証明することであり、悪魔の証明ともいわれています。
このようなおよそ不可能に近い証明に失敗したために被告人に刑罰という不利益を科するわけにはいきません。そこで、刑事手続きでは「疑わしきは被告人の利益に」の原則の下、被告人が犯人であることや犯罪事実の立証責任は検察官が負っています。
検察官は、被告人が犯人であり、犯罪事実を犯したことを合理的な疑いを入れない程度まで証明しなければなりません。一方、被告人及び弁護人としては、被告人の無実を証明する必要はなく、検察官の立証に疑いをさしはさめればそれで十分なのです。
検察官が、被告人が犯人であることや、犯罪事実を立証できなければ、犯罪の証明がないとして、裁判所は無罪の言渡しをしなければなりません(刑事訴訟法336条)。裁判所も「犯罪事実の証明はなかった」と触れるだけで、積極的に被告人は犯人ではなかったとか被告人は犯罪を犯していないなどまでは言及しません。
勾留からの解放について
勾留の有無は被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることを前提に勾留の理由と必要性とによって判断します。勾留の理由は逃亡や罪証隠滅のおそれであり、被疑者が実際に罪を犯したかどうかとは別のものです。勾留の必要性も被疑者を勾留しなければならない理由の重さや勾留により被疑者等が負う不利益を考慮して判断されるものです。勾留が取り消されても、勾留の要件が無かったことを意味するに過ぎず、被疑者の犯罪事実の有無を宣言するものではありません。
勾留決定に対する準抗告では、犯罪の嫌疑がないことを理由として準抗告をすることはできないと定められています(刑事訴訟法420条3項・429条2項・429条1項2号)。これについては、被告人となったならば犯罪の嫌疑は公判で決すべきであるので勾留にて争うのは相当ではないが、被疑者のときはそのような状況になく、420条3項は公訴提起後のみ準用され、公訴提起前の被疑者勾留につては準用されないという主張があります。
不起訴-起訴便宜主義
不起訴となっても実は無実を示したことにはなりません。検察官が嫌疑なしの場合のみならず、嫌疑不十分つまり合理的な疑いを超えた立証ができる確信に至らなかった場合も不起訴とすることがあります。また、嫌疑が十分にあっても、犯罪の軽重や情状などを考慮して起訴しないこともあります。
これらの不起訴処分はいずれも起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)に基づきます。不起訴の場合には、検察庁は請求すれば不起訴処分告知書を出してくれますが、不起訴の理由について特に記載されないため、検察官が被疑者は無実だと判断したかどうかは分かりません。