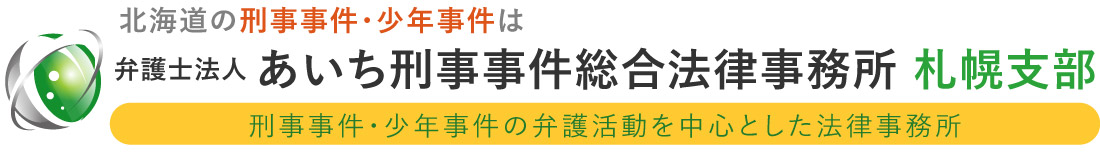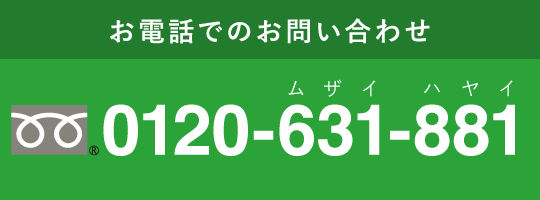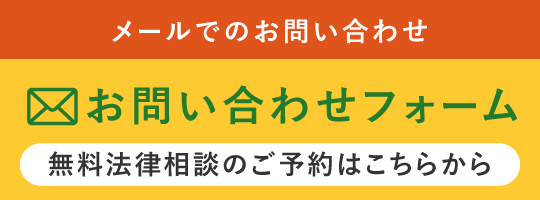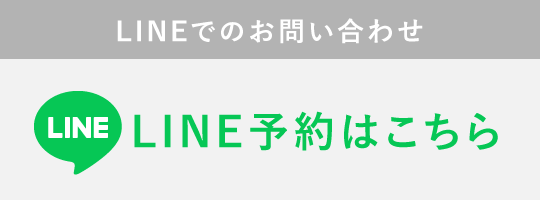逮捕されている間
 逮捕自体には不服申し立ての手続きがありません。したがって、法律上は、逮捕による身柄拘束中に逮捕について争うことはできません。弁護士が検察官と交渉して逮捕の違法性を指摘し、あるいは即日被害者と示談をして、逮捕中に釈放してもらうこともあり得ないことはないですが、極めて難しいことです。本格的に争うのは勾留手続きに入るときです。
逮捕自体には不服申し立ての手続きがありません。したがって、法律上は、逮捕による身柄拘束中に逮捕について争うことはできません。弁護士が検察官と交渉して逮捕の違法性を指摘し、あるいは即日被害者と示談をして、逮捕中に釈放してもらうこともあり得ないことはないですが、極めて難しいことです。本格的に争うのは勾留手続きに入るときです。
勾留
検察官は被疑者を逮捕してから72時間以内に勾留請求をしなければなりません(刑事訴訟法203条、204条、205条1項・2項)。勾留請求をしてから、決定が出るまでは、身柄拘束の継続が続きます。勾留は原則として10日(刑事訴訟法208条1項)、延長されるとさらに10日(同2項)身柄拘束が続くことになります。この起算日は検察官が勾留請求をした日からです。検察官はこの間に被疑者を起訴するかどうかを決めます。
どのようなときに勾留されるのか
勾留の理由
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に、勾留の理由がある場合に勾留されます(刑事訴訟法60条1項・208条1項。60条は起訴された後の被告人勾留に関する規定ですが、208条1項により起訴前の被疑者勾留についても同じように扱うことになっており、「被告人」は「被疑者」と読み替えられます。)。
60条1項1号に定められている「被疑者が定まった住所を有しないとき」は明らかであることが多く、問題になるのは2号の「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」と3号の「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です。これらの勾留の理由は客観的な事情と被疑者の主観面を総合して判断されます。
逃亡のおそれは、犯罪の被害や悪質さから予測される刑の重さ、被疑者の収入、勤務態度、現在の住居への定着の程度、家族との関係、などを総合的に考慮されて決められます。犯罪が重大との簡単な理由で認められることが多いです。
罪証隠滅のおそれとは、犯罪の証拠を隠滅するおそれです。凶器を持ち去る、カメラの映像を消すなどを思い浮かべると思います。その他にも、人の証言も証拠ですので、目撃者の家に押し掛けて見ていないと言わせることも罪証隠滅に当たります。これも被害者に接触するおそれがあるなど抽象的な理由で認められることが多いです。
弁護士は犯罪の性質、被疑者の生活、考え得る証拠などあらゆる事情を精査して逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
勾留の必要
勾留の理由があるだけでは勾留することはできず、勾留の必要がなければならないとされています。勾留の理由の程度や身柄を拘束せずに捜査する(このような事件は「在宅事件」と言われます。)ことが十分にできるかどうか、勾留されることによる被疑者や第三者の不利益などを総合的に考慮されて決まります。
勾留阻止
裁判官は勾留の要件を満たさない場合は勾留請求を却下します。ただ、近年までは、逃亡や罪証隠滅のおそれが抽象的なものにとどまる場合でも勾留決定をしてきました。最近では勾留請求を却下する例も増えてきましたが、漫然と勾留決定をする例はまだまだ見られます。
勾留される前に弁護士が選任されていれば、弁護士は、裁判官が勾留決定をする前に裁判官に意見書を提出したり裁判官と面談するなどして、被疑者には逃亡も罪証隠滅のおそれもなく勾留の必要もないことを訴え、裁判官に勾留請求却下の判断を促すことができます。
準抗告
勾留決定がされた場合、その決定を争うことができます。これを準抗告といいます(刑事訴訟法429条1項2号。「勾留に関する裁判」以外の決定についても準抗告ができます)。勾留延長決定も「勾留に関する裁判」であるため準抗告ができます。
勾留の理由、勾留の必要がないことを訴えて、勾留の決定の取り消しを求めます。
準抗告においては、勾留の決定をした裁判官とは別の裁判官で構成される裁判所が判断します。とはいえ、裁判官が判断したものと他の裁判官が判断したものとの結果が異なることは少なく、準抗告が認容されて勾留決定が取り消されることは多くはありません。最初の裁判官の判断である勾留決定のときに効果的な弁護活動を行い、そもそも勾留決定をさせないことが重要となります。
勾留却下決定に対して検察官が準抗告した場合
勾留請求却下決定も「勾留に関する裁判」であるため、検察官は、勾留却下決定に不服があれば、準抗告をする可能性があります。検察官が準抗告をしたかどうかは何もしなければ弁護士に教えてくれないこともあるため、弁護士から検察官に準抗告をする意思があるのかを問い合わせ、検察官が準抗告をする意思であれば準抗告に対処することになります。
なぜなら、勾留請求却下決定の取り消し及び勾留状の発布を求めると同時に、検察官は勾留請求却下の裁判の執行停止を求めることが多いからです。刑事訴訟法207条4項但書で「ただし、勾留の理由がないと認めるとき、…は、勾留場を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」と定められていることから、勾留請求却下決定と同時に被疑者を釈放するよう命じる「釈放命令」が出されていると解し、この「釈放命令」の執行の停止を求めるというのです。
これでは、準抗告に対する決定が出るまで、身柄拘束は続くことになります。弁護士は検察官が準抗告すれば、検察官の申立書の閲覧・謄写を行い検察官の主張を精査し、準抗告裁判所の裁判官と面談して「釈放命令の執行停止」をせず被疑者を釈放させるよう求め、裁判所が準抗告を却下するよう積極的に活動します。
勾留延長の阻止
勾留は延長を含めて20日ですが、検察官は最初からこの20日を前提に捜査を進めているかのように勾留延長を請求します。刑事訴訟法208条2項は「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」と定め、最長10日の勾留延長請求を認めています。
「やむを得ない事由があると認めるとき」という文言にもかかわらず、取調べがまだ終わっていないなどの理由で、容易に勾留延長が認められているのが現状です。弁護士は勾留の延長の理由も必要もないことを主張して、勾留延長決定の却下を求めます。さらに、被害者との示談を成立させるなど勾留の理由や必要を低下させる活動も積極的に行っていきます。
勾留延長決定に対する準抗告
勾留の延長の決定も「勾留に関する裁判」であるため、準抗告をすることができます。もととなる勾留が認められてきたためか、こちらも認容されることは多くはありません。
勾留の取消し
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判官は、検察官や勾留されている被疑者やその弁護人などの請求により、または職権で、勾留取り消し決定をしなければなりません(刑事訴訟法87条・207条1項)。
勾留の執行停止
裁判官は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被疑者を親族などに委託したり、被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができます(刑事訴訟法95条・207条1項)。重大な疾病で留置場の中にいるのに耐えられない場合などです。
国選弁護人の場合
国選弁護人が選任されるのは、被疑者に対する勾留状がだされた後です(刑事訴訟法37条の2)。国選弁護人が身柄釈放活動を行うことができるのは勾留の準抗告からとなります。上でも散々述べた通り、身柄の解放活動が遅れるほど覆すことは困難になります。
私選弁護人の場合
私選弁護人はどのタイミングでも選任できます。逮捕直後勾留請求前の段階から弁護人を選任することもできます。勾留請求前にご家族から詳細に事情を伺い上申書や身元引受書を裁判官に提出し、弁護士が裁判官と面談して勾留の理由や必要性がないことを訴え、勾留決定を回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見のご依頼を受ければ即日弁護士が初回接見を行い、その日のうちにご家族に接見報告を行います。同日中に契約することで、勾留決定前に迅速かつ的確な弁護活動を行い、勾留決定を回避します。
もしご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へお問い合わせください。