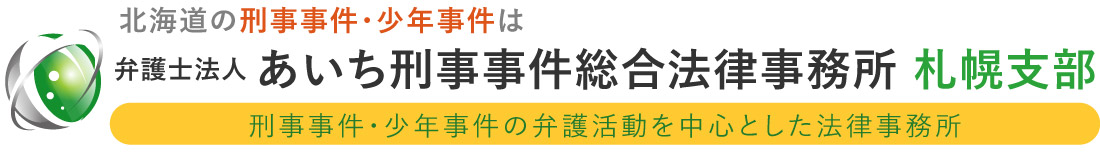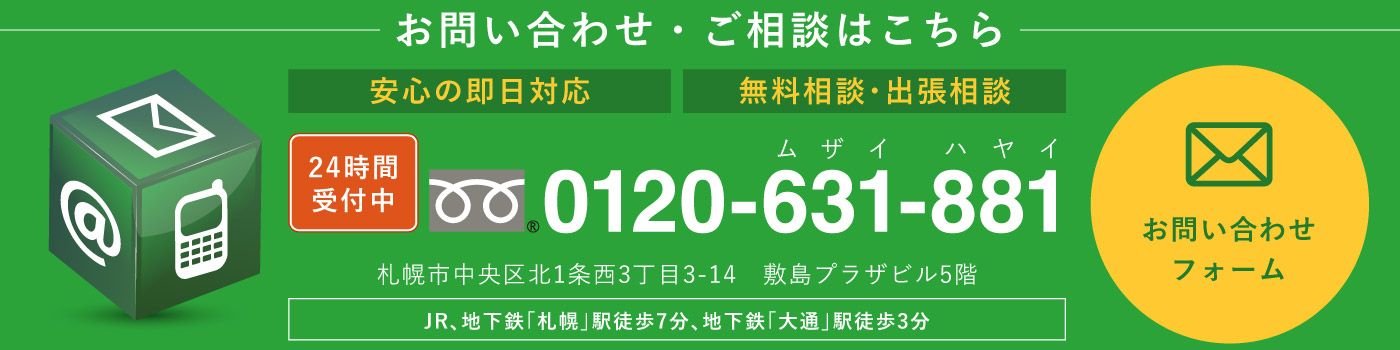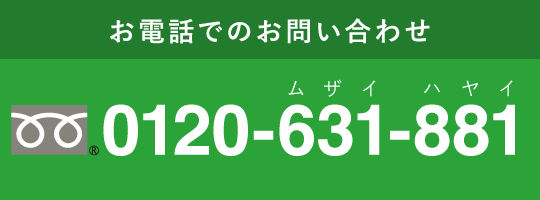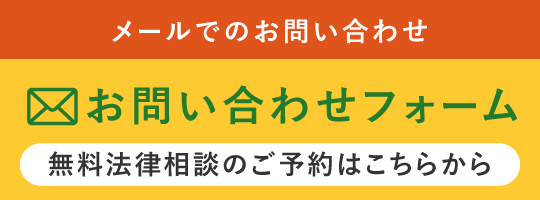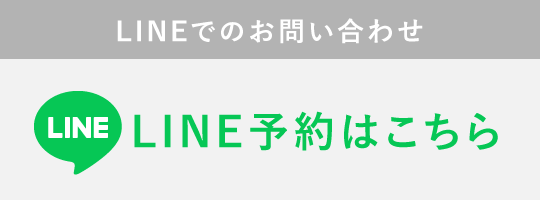※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
大麻事件の概説と法定刑
大麻取締法が大幅に改正され、名称も「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更になりました。同法は主として大麻草の栽培規制に関する内容のみを定めるものとなりました。
「大麻」とは、「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう」と規定されました。
大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。営利の目的で大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上の有期拘禁刑に処され、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処されます。未遂も罰せられます。以前より法定刑が重くなっております。
大麻に関する主な罰則は、「麻薬及び向精神薬取締法」に規定されることになりました。
改正後は、大麻の所持だけでなく、施用(使用)も処罰されることになりました。施用(使用)したら7年以下の拘禁刑となります。
大麻を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の拘禁刑に処されます。営利の目的のときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処され、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処されることになります。未遂も処罰されます。以前より実質的に法定刑が引き上げられております。
大麻を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。営利の目的のときは、1年以上の有期拘禁刑に処され、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処されます。未遂も処罰されます。
このような法改正がなされた背景として、大麻使用者が社会に蔓延しており、再犯者も多いことがあります。司法・行政は大麻に対してより厳しい態度で臨むことになりました。逮捕・勾留され、身体拘束の期間もより長くなるかもしれません。実刑判決を受けて刑務所に入ることも多くなり、その期間も長くなる可能性があります。
大麻事件の刑事弁護活動
1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず、大麻関連犯罪の容疑を掛けられてしまうことがあります。弁護士を通じて、警察・検察に働きかけて不起訴を主張したり、裁判で無罪を訴える必要があります。
特に、対象物が大麻であることの故意が無ければ犯罪は成立しません。大麻やその他の違法薬物である認識が無かったのであれば、それを裏付ける証拠を集める必要があります。
2 違法収集証拠の排除を主張する
実際に大麻関連犯罪をしてしまったとしても、捜査の過程で重大な違法があれば、違法収集証拠として証拠能力を否定し、不起訴や無罪になる可能性があります。捜査過程の適法性についても厳しく検討する必要があります。
3 量刑を軽減するような弁護活動
犯罪の成立に争いが無ければ、依存性・常習性の程度、再犯のおそれ、共犯事件の犯行の役割・立場等でこちらに有利な主張をして、量刑を軽くするように訴えていきます。
特に、再犯防止対策は重要で、家族や病院の助けを受けながら治療に努め、2度と大麻に手を出さないことを誓うことになります。
4 釈放や保釈による身体拘束を解くための弁護活動
逮捕・勾留された場合には、釈放・保釈を実現させることが重要です。逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことを主張していくことになります。家族に身元引受人になってもらい、監督・監視していただき、協力して身体拘束解放を訴えていくことになります。